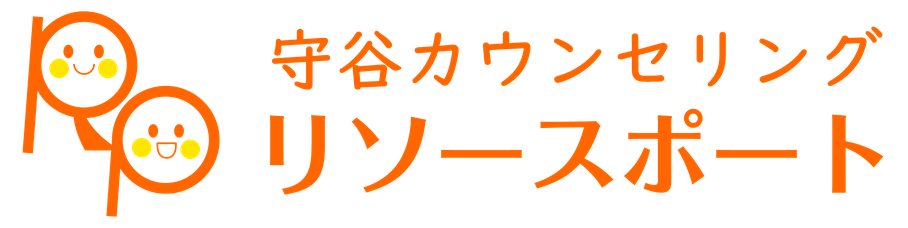お子様がスマホをずっと使い続けている様子を見て、心や脳に悪影響ではないかととご心配になっている保護者様が多いのではないかと思います。
宿題を全くやらなくなったり、寝る時間が遅くなったり、歯みがきやお風呂なども何度言ってもやらなかったりすることが多いと思います。
そばで見ている保護者様としては、イライラしたり、腹が立ったり、ガッカリしたりなど、いやな気持ちになってしまうと思います。
言っても言って変わらないので、「スマホを取り上げるのが良いのではないか」と思うこともあるかもしれません。
スマホをやめられない場合、スマホを取り上げた方が良いかどうかについて解説しました。

逆効果で悪影響が残るパターン
小学校高学年から中学生ぐらいになると、スマホ(ゲーム)をずっとやり続けていて、親が何度言っても聞かないということが生じがちです。
その場合に、親がスマホ(ゲーム)を無理矢理取り上げたりすることは、基本的にお勧めできません。逆効果で悪影響が心配だからです。無理矢理取り上げてやめさせることが続いていると、いつも親が取り上げてやめさせないとスマホをやめられないようになってしまいます。
また、スマホ(ゲーム)を取り上げたときに、子どもが逆ギレして暴れることもよくあります。子どもが暴れると取り上げにくくなってしまい、結果的にスマホ(ゲーム)が野放しになってしまうリスクもあります。
さらには、親子関係も険悪になって、スマホ(ゲーム)をやり過ぎると言うことだけではなく、勉強や生活、友達関係など様々な面に悪影響が出てくる可能性もあります。
こんなふうに無理矢理取り上げてやめさせることは、様々な悪影響が生じるリスクがあるのです。
スマホやゲームを【 やめる力 】が必要
少し話しがそれますが、私が子どもの頃は、好きなテレビ番組は必ず30分や60分の決まった時間で終わりました。どんなんに見たくても、それ以上見ることはできず、また次の週まで待たなくてはなりませんでした。
しかし、今の子どもたちは全く事情が違っています。スマホで面白い動画を1つ見たら、次から次に面白そうな動画をおすすめされます。そして、本当に無限に楽しい動画を見続けることができるのです。
ゲームも同じです。何度でも何時間でも延々と遊び続けられるようにゲームは作られています。飽きさせないように、止められないようになっているのです。
こんなふうに、昔と今では子どもたちの置かれている状況が全く違っているのです。昔は、何か和やめなくてはならないと考え、やめる行動をする必要はなく、そもそも続けることそのものが難しかったのです。
つまり、昔は「やめる力」は必要ではなかったのです。
そして、今は「やめる力」が必要です。
スマホやゲームを【 やめる力 】を育てるには
「やめる力」を育てるには、どんなふうに関わることが必要でしょうか?
答えは簡単です。無理にやめさせたり、取り上げたりするのではなく、子どもが自分からスマホ(ゲーム)をやめるように促すことが大切です。少し促してみて、自分からやめられたら、自分からやめられたことをほめてあげるのです。
また、スマホ(ゲーム)をやめたときには、あらかじめ決めた場所にスマホ(ゲーム)を置くようにします。
促しただけで、そんなことができたら苦労しないと思う方が多いかもしれません。具体例をもとに考えていきます。
例えば、「もう8時だよ! スマホ(ゲーム)をやめる時間だよ」とお子様に促したあとに、動きがないので数分後にもう一度「もう8時だよ! スマホ(ゲーム)をやめる時間だよ」と促します。
そこから、さらに10分ぐらいして、お子様がスマホをやめて動きが出ます。その時に「決められた場所に置いて」と促します。
その言葉に応えて、お子様がスマホ(ゲーム)を決められた場所に置いたら「自分で終わりにできてえらいね」「自分で終わりにして素晴らしい」などとほめます。
やめたことをほめるのが大切です
上に書いたように、スマホ(ゲーム)をやめることは非常に難しいのです。そのため、スマホ(ゲーム)を終わりにするまでに、少しぐらい時間がかかったとしても、仕方がないのです。
だからこそ、スマホ(ゲーム)を「自分で終わりにしたのが素晴らしいね」などとほめることが大切です。
時間がかかったことに対して、「もっと早くやめなさい」などと叱ったりすることは、お勧めできません。スマホを終わりにするということはただでさえ不快なことです。それに加えて叱られるのは、非常に不快な気持ちになります。
つまり、お子様は、スマホを終わりにすることで非常にイヤな気持ちになるという体験をすることになります。
【スマホ(ゲーム)をやめる】=【いやな気持ちになる】というつながりが脳の中にできてしまいます。
だからこそ、スマホ(ゲーム)を終わりにできたときには、しっかりほめてあげることが大切なのです。
そうすると脳の中に【スマホ(ゲーム)をやめる】=【プラスの気持ちになる】というつながりができるのです。
そうなれば、やめることに対する抵抗感が小さくなります。
まとめ
スマホ(ゲーム)取り上げるのは、スマホをやめる力つかないので、逆効果です。
スマホ(ゲーム)を(時間がかかっても)やめられたときに、「自分で終わりにできてすばらしい」などとほめてあげるのが、良い方法です。
脳の中に、【スマホ(ゲーム)をやめること】と【プラスの気持ち】のつながりが生まれ、スマホをやめるときの不快感が減少するのです。
この文章は、半田一郎(公認心理師・臨床心理士・学校心理士スーパーバイザー)が執筆しました。
こちらの記事もお読みください
スマホだけを問題にしても、スマホ依存を予防することはなかなか難しいものです。スマホを使うときのルール作りが大切と言われています。ルールの内容も大切ですがルールの決め方やル0ルが守られなかった時の対処を事前に話し合っておくことも大切です。
スマホにはまってしまうと、生活習慣がどんどん崩れてきます。そうなってから対処するのではなく、スマホを買う前に親子で生活習慣について話し合っておくことをお勧めします。