不登校など学校に行きづらい子どもが増えています。令和5年(2023年)10月に発表された「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文部科学省)」によれば、不登校の子どもたちの数は、小学生では105,112人、中学生では193,936人の合計299,048人となっています。前年度から約22%も増加しています。なお、令和元年度では合計181,272人、令和2年度では合計196,127人、令和3年度では合計244,940人でした。
なお、低学年ほど増加が著しく状況です。例えば小学校1年生では、令和4年度は令和元年度の2.43倍です。学年が上がるにつれて、増加率は少なくなっています。
文部科学省や市町村教育委員会、それぞれの学校では学校に行きづらい子どもたちのために、色々な工夫を考えています。そのひとつが校内フリースクールです。
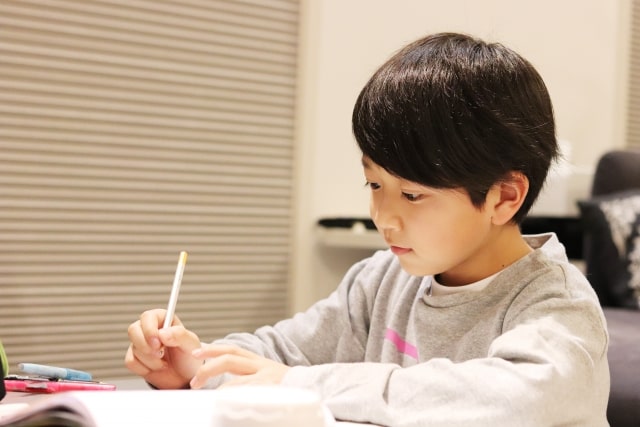
校内フリースクールとは
校内フリースクールとは、小学校や中学校の空き教室を活用して、教室に居づらい子どもや学校に行きづらい子どもたちが過ごせるような居場所を作って、担当する職員を配置して子どもたちのサポートを行う仕組みです。子どもたちは、自由な時間に登校してきて、担当の職員と相談してその日の活動を決めて、自分で学習したり教室の学習に(オンラインで)参加したり、友達と関わったりします。
今まで通っていた自分の学校の中にあるので、子どもたちにとっては利用しやすい考えられます。また、利用のための特別な費用はかかりませんし、出席日数にカウントされることも大きな利点だと考えられます。
参考
校内教育支援センターとは違うの?
文部科学省はCOCOLOプラン(R5年3月)の中で、校内フリースクールという名称ではなく【校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)】という名称を使っています。また、【校内適応指導教室】という言葉も使われることがあります。
【校内フリースクール】【校内教育支援センター】【校内適応指導教室】という言葉はどれも、ほとんど同じ意味で使われています。
なお、【校内フリースクール】は【校内FS】と略されることがあります。
ここでは、一般によく使われている校内フリースクールという言葉を使っていきます。
校内フリースクールの特徴
- 担当の先生やスタッフがいて勉強や活動のサポートしてくれる
- リラックスできるような場所(じゅうたん敷き、ソファーなど)がある
- 利用している子どもが少ないため、落ち着いた雰囲気になっている
- 自分でその日に何をするかを決めて活動する
- 登校と下校の時間は決まっていないため、自分で決めて登下校する
- 給食を食べることができる
- 教室での学習や活動に参加することができる
- トランプやオセロなどちょっとしたゲームでも遊べる
- 部活動に参加することも可能
- 利用のための費用がかからない
- 出席扱いとなる
子どもたちの感想や反応
- 少人数で安心できる場所があると学校に来ることができる。
- 静かに自分のペースで学習ができる。教室はざわざわしている。
- 校内フリースクールがあったので,教室でしんどくなった時も家に帰らずに校内フリースクールに行くという選択肢が増えたことが良かった。
- 体がしんどい時,みんなと同じペースで勉強が,進められない時に校内フリースクールを使って自分のペースで勉強し,また教室に戻れるのが良かった。
- 授業の途中で教室から出たり,教室に入ったりするのは特に気にならないようになった。
- 校内フリースクールでは,周りの人に助けてくれる友達ができて笑顔になれる。友達が困ったときに助けてくれる。
- 人の気持ちを考えることができるようになった。
校内フリースクールと別室登校の違い
校内フリースクールと別室登校の一番の違いは、担当する職員が配置されているかどうかです。
別室登校は、空いている教室を一時的に居場所にするという面が強いため、担当してる職員はいません。担任の先生やたまたま空き時間になっている先生が対応してくれるだけです。そのため、利用している子どもたちとじっくりおしゃべりをしたり、時間をかけて勉強を教えたりすることは難しい場合がほとんどです。別室登校に通っている子どもたちが、自分一人で過ごすような時間が多くなりがちです。
校内フリースクールでは、きちんと予算をつけて職員を雇用しています。その職員は授業を担当したり、クラスの担任だったり、学校内のその他の役割を担っているわけではないので、校内フリースクールのことだけに時間を使えます。そのため、職員が子どもたちとおしゃべりをしたり、相談に乗ったり、勉強を教えたりすることにも時間をかけらられます。また、子どもだけでは、子ども同士の関係を深めていくことは難しい面がありますが、担当の職員がいれば子ども同士の関係をつなぐことも、できると思います。
別室登校については以下のリンク先をご参照ください。
子どもにとっての校内フリースクールのメリット
子どもにとっての、校内フリースクールのメリットは、なんと言っても自分の学校の中にあるということです。教室に行きづらくなった時や不登校になった時に、学校外の適応指導教室(教育支援センター)や民間のフリースクールも利用することができますが、それらは子どもにとっては知らない場所です。知らない場所に通うことは、少なくとも最初は子どもにはいろいろな負担がかかると思います。教室に行きづらい状態や不登校の状態になっているわけですので、ただでさえ辛い思いをしています。さらに負担がかかることを始めるのはなかなか難しいと思います。そういう意味で、自分の学校の中にある校内フリースクールは子どもたちにとっては利用しやすいと思います。
また、自分の学校の中にあることは、基本的に自力で通える範囲にあるということです。行きやすいということよりも、帰りやすいことが重要です。登校の時には、ある程度計画的に登校してくると思いますので、家族の誰かに送ってもらいやすいと思います。ただ、学校で過ごしているうちに疲れてしまって帰りたくなるなどのことは、良くあります。そういう予定していない時に、迎えに来てもらうのはなかなか難しいことが多いと思います。そういう場合にも、自力で通える範囲にあれば自力で帰宅できる可能性があります。それは非常に大切なポイントです。実は、自力でも帰れる場所にあるからこそ、いざとなったら帰れるという安心感が高まります。そのため、来るときのハードルが下がるのです。
また、自分の学級での学習や授業以外の活動にも参加しやすいという面があります。教室にいる仲の良い友達とも会って話す機会も得やすいと思います。こういったことも、子どもには大きな利点だと思います。
保護者にとっての校内フリースクールのメリット
保護者にとっても校内フリースクールは様々な利点があります。子どもが通う場所を探さなくて良いという点は大きな利点だと思います。学校外の施設や機関は色々ありますが、それを探して子どもに合うかどうかを考えて、実際に子どもを連れて行くなどして、子どもと一緒に検討することは保護者に大きな負担となります。
また、送り迎えの時間が(余り)かからないことや、行き帰りにトラブルが生じるのではないかという心配が少ないと思います。費用面でも、特別な負担はありませんので、それも保護者にとっては大きな利点だと思います。
実践報告
校内フリースクールがどのように運営されているか、なかなか実態がわかりにくいと思います。いくつかの実践報告が論文としてまとめられていますので、紹介します。以下の大学のリポジトリのページからPDFをダウンロードしてご参照ください。
中学校での校内適応指導教室の実践例をもとにして、学校としての動き方やシステムについて論じられています。まとめとして以下の3点が指摘されています。
・居場所づくりが必要
校内に適応教室があることで、学級に不適応をおこしても校内に居場所があるという安心感をもつことができる。学級で過ごしている生徒と適応教室の生徒に交流が生まれて、生徒間のつながりとなり学級復帰のきっかけの1つとなることもある。学校によって別室での支援を必要とする生徒やニーズ、利用できる部屋もちがうため、学校の現状に応じた居場所作りが必要である。
・異なる立場の人がチームになって支援することが必要
4種類のヘルパー①専門的ヘルパー(SC・校内適応教室担当者)②複合的ヘルパー(教員)③役割的ヘルパー(保護者)④ボランティア的ヘルパー(支援ボランティア)といった立場の違う支援者がそれぞれの役割を担いつつチームとなって支援を行うことが重要。教員やボランティア的ヘルパーを確保できるかの課題もあるが、学校内外の人的資源を有効に活用する必要がある。
・管理職を含む学校内の組織の働きが重要
管理職、学年主任、生徒支援推進委員会コーディネーター(代表)、SCを構成員とする生徒支援のための委員会を設置し、週1回程度定期的に時間を取って情報共有や支援について話し合うことが重要。学校内で連携する援助システムが整備されることで効果的な援助活動が行えると考えられる。
中学校内に設置された校内適応指導教室の実践の内容を具体的に紹介してます。実際の教室の写真、申請書や承諾書、日誌の具体例が紹介されています。実際のことが具体的にわかるので、実践に役立つ論文だと思います。
校内フリースクールでの支援活動
では、実際の校内フリースクールではどのような活動が重視されているかを見てみます。
『平成19年度学位論文 校内適応教室における連携の影響~必要とされる支援や連携から今後の校内適応教室のあり方を探る』(兵庫教育大学大学院学校教育研究科 園田和広)という研究がありましたので、そこから抜粋して紹介します。
2006年度について調査した結果に基づいた研究なので、現在は状況が変わっていると思いますが、参考になると思います。
校内フリースクールでどういった支援活動が必要とされていて、どの程度行われているかを理解することができます。
以下の表は、「必要度」が高い順に項目を並べてあります。校内フリースクールでは、特に上位に位置する支援を行っていくことが求められると思います。その中でも、達成度が高い項目は、必要だと思われている上に、実際に行われた支援活動です。こういった活動は極めて重要だと思います。
保護者の立場として考えると、子どもが校内フリースクールを利用しているのに、今ひとつプラスになっていない等の場合には、こういった項目を参考に、学校と情報交換をすると良いかもしれません。
校内フリースクールの担当者として考えると、まずはこういった項目を眺めてみて、きちんと実践できているかを振り返ってみることが必要だと思います。その上で足りないところを補っていくことが大切だと考えられます。
|
|
達成度順位 | 必要度順位 |
| 子どもの心の理解 | 3 | 1 |
| 子どもとの人間関係作り | 1 | 2 |
| 支援の中で子どもの悩みを聞くこと | 2 | 3 |
| 子どもに自信をもたせること | 4 | 4 |
| 社会性・協調性の育成 | 11 | 5 |
| 基本的生活習慣の育成 | 6 | 6 |
| 自主性主体性の育成 | 9 | 7 |
| 学力の維持・保障を目指した学習支援 | 10 | 8 |
| 個別の教育プログラムや支援計画の実施 | 17 | 9 |
| がまんする心の育成 | 13 | 10 |
| 少人数授業形式による学習支援 | 12 | 11 |
| 1対1での学習支援 | 7 | 12 |
| 集団活動を多く取り入れること | 16 | 13 |
| 子どもの自主性に任せた学習支援 | 5 | 14 |
| 遊びやゲームを通して友人とふれあう場の設定 | 18 | 15 |
| できるだけ時間割に沿った学習支援 | 15 | 16 |
| 創作活動を多く取り入れること | 19 | 17 |
| 遊びやゲームを通して職員とふれあう場の設定 | 14 | 18 |
| 子どもが自由にできる時間の設定 | 8 | 19 |
校内フリースクールでの連携活動
校内フリースクールでは、学校内の他の職員と連携したり、保護者と情報交換・意見交換したりすることが重要です。こういった連携活動では、どういった活動が必要とされていて、どの程度行われているかを見ていきたいと思います。
以下の表は、「必要度」が高い順に項目を並べてあります。校内フリースクールでは、特に上位になっている支援を行っていくことが求められると思います。その中でも、達成度が高い項目は、必要だと思われている上に、実際に行われた支援活動です。こういった活動は極めて重要だと思います。
保護者との連携に関する項目が必要度が高く達成度も高くなっています。保護者との連携は非常に重要な活動だと言えると大見ます。もし、校内フリースクールを利用しているのに学校との連絡や情報共有が少ない場合は、こういった項目を参考にして、学校と話し合ってみるのも良いかもしれません。
校内フリースクールの担当者として考えると、まずはこういった項目を眺めてみて、きちんと実践できているかを振り返ってみることが必要だと思います。その上で足りないところを補っていくことが大切だと考えられます。
|
|
達成度順位 | 必要度順位 |
| 担当職員内での役割分担や支援活動の意図についての共通理解 | 5 | 1 |
| 職員会議などで活動内容や子どもの状況を報告すること | 7 | 2 |
| 保護者と必要に応じて電話、 手紙、 メールなどで連絡を取り合うこと | 2 | 3 |
| 全職員間での役割分担や支援活動の意図についての共通理解 | 10 | 4 |
| 保護者への必要に応じた面接や家庭訪問 | 4 | 5 |
| 不登校対策委員会などの運営 | 13 | 6 |
| 保護者の希望や様子についての情報交換 | 6 | 7 |
| 不登校担当や担任など特定の職員以外の職員も支援にあたること | 9 | 8 |
| スクールカウンセラーと支援内容を随時検討すること | 3 | 9 |
| スクールカウンセラーを交えた支援内容の検討会議 | 12 | 10 |
| スクールカウンセラーによる子どもへのカウンセリング | 1 | 11 |
| 子どもの卒業園・校から情報収集すること | 14 | 12 |
| 不登校担当や担任など特定の職員以外の職員も子どもの情報収集をすること | 11 | 13 |
| 休み時間や空き時間など短い時間を利用した報告や情報交換 | 8 | 14 |
| 子どもの理解や支援内容の検討のための定例会議 | 16 | 15 |
| 子どもの個人ファイルや日誌などを利用した情報交換 | 19 | 16 |
| 多くの職員が子どもとふれあうこと | 15 | 17 |
| 教育センターなどの公的機関(訪問指導員を含む)と情報交換し支援内容を検討すること | 17 | 18 |
| 教育センターなどの公的機関で支援を行うこと | 18 | 19 |
| 教育センターなどの公的機関との定期的な連絡会議 | 20 | 20 |
| 支援活動の一環として地域の人材や施設を利用すること | 22 | 21 |
| 子どもの理解や支援内容の検討のための臨時会議 | 21 | 22 |
| 別室についての意識啓発のために相談室だよりなどを作成すること | 23 | 23 |
最後に
こんなふうに、校内フリースクールは子どもたちにとっても、保護者にとっても、様々な利点があります。ぜひ、全国の全ての小中学校に開設してほしいと思います。
小規模な学校を複数組み合わせて、1人の職員が月(1日)、水(午前)、木(1日)はA小学校、火(1日)、水(午後)、金(1日)はB小学校に勤務して2つの小学校で校内フリースクールを開設するという方法もあると思います。今通っている学校に校内フリースクールがあることは、子どもたちにとってのプラス面が大きいと思いますので、ぜひ、組み合わせる形でも実施できると良いのではないかと思います。
また、職員には教員経験者だけではなく、心理職を雇用することも良い方法だと思います。例えば、スクールカウンセラーを常勤にして、週に2日は今まで通りのスクールカウンセラーとして仕事をして、週に3日は校内フリースクールをメインに仕事をするという方法も良いのではないかと思います。
この記事の執筆
半田一郎(公認心理師・臨床心理士・学校心理士スーパーバイザー)
更新日:
